〜探究心を育む保育実践〜
はじめに
保育の現場で子どもたちと一緒に育てる経験は、どれも特別なものです。特に、子どもたちが主体となり、興味を持って進めていく活動は大きな学びになります。昨年度、5歳児クラスで行った「てんとう虫の飼育」という探究活動を通して、子どもたちがどのように学び、成長したのかを紹介します。
※この記事には広告(PR)が含まれています。保育実践で実際に使用したものです。
子どもたちの「やってみたい!」から始まった探究活動
4月中旬、公園で見つけたてんとう虫の卵。子どもたちはそれを見つけた瞬間、「飼ってみたい!」と興奮気味に話し始めました。この時点で、子どもたちの探究心が芽生えたのです。私たち保育者は、どうやってその興味を広げていこうかと考えました。
絵本や図鑑で学ぶ「てんとう虫」の世界
まず、子どもたちが興味を深められるように、絵本や図鑑を使って調べていくことにしました。福音館の『わたしのちいさないきものえん』や『てんとうむしみつけた』、フレーベル館の『しぜん④てんとうむし』、小学館の『図鑑NEO昆虫』などを一緒に見ながら、てんとう虫の生活について学びました。
ここで私が心がけていたのは、正解を直接教えるのではなく、子どもたちの気づきに共感し、必要な情報を見つけるための質問をすることでした。例えば、子どもが「てんとう虫は幼虫もアブラムシを食べるんだって!」と言ったとき、私は「すごいね、よく見つけたね。それでアブラムシはどこにいるの?」と問いかけ、子どもたちが自分で調べ始めるきっかけを作りました。こうした過程を通じて、子どもたちは自分で情報を探す楽しさや達成感を感じ、自己肯定感を育んでいきました。
飼育環境を作り、てんとう虫の成長を見守る
てんとう虫の卵を持ち帰り、飼育環境を作りました。卵がついている枝や葉をペットボトルに入れ、水切りネットで包むことで、飛び出さないように工夫しました。孵化後は虫カゴに移し、アブラムシのついた植物を入れて栄養を与えることにしました。
興味深いのは、子どもたちが積極的に家庭で調べ、アブラムシがつきやすい植物をリストアップしてきたことです。「これが必要だよ!」と、子どもたちが自主的に行動する姿勢に驚きました。私たちはその植物を戸外で探し、ビニール袋に入れて持ち帰りました。こうして、てんとう虫の食事も調達していきました。
失敗から学ぶこと
活動が進む中で、予想外の出来事もありました。アブラムシが足りず、てんとう虫たちは共食いを始め、最終的に1匹だけが残ることに。その子は「ボス」と命名され、子どもたちはその後も「ボス」を大事に観察し続けました。
この出来事から、命の大切さや、自然界での生き物同士の関係を学ぶことができました。子どもたちは「お腹が空いてたのかな?」と共感し、ボスの行動に思いを馳せていました。このような感情移入が、子どもたちにとって貴重な学びになったことを感じました。
脱皮や蛹の変化にワクワク
また、脱皮や蛹になる瞬間を見つけた子どもたちは、いち早く教えてくれました。「こっち来て!」「虫眼鏡貸して!」と、順番に観察していた光景が印象的です。毎日観察する中で、「今日も元気そう!」と毎朝チェックすることで、子どもたちの成長への関心が深まっていきました。
おわりに
この活動を通して、子どもたちは「探究心」「自己表現」「共感」「命の大切さ」を学びました。何より、子どもたち自身が主体となって進めていく活動だからこそ、彼らの学びは深く、記憶に残るものとなったと感じます。
保育者としては、子どもたちが自分で考え、感じ、学べる場を提供することが何より大切だと再認識しました。これからも、子どもたちの「やってみたい!」を大切にしていきたいと思います。
▽春の自然遊びについての記事はこちら
🌷子どもと一緒に楽しむ!春の自然あそび特集|花であそぶ・つくる・観察する
他の保育実践記事はこちら▷準備中
▽虫メガネがあると探求意欲が増し、おすすめです。




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46c1d765.6107ad6a.46c1d766.74390516/?me_id=1216060&item_id=10001329&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fslowworks%2Fcabinet%2Fnavir%2F1484824_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


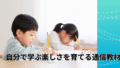
コメント