前回の記事はこちら▽

子どもと関わりたい。でもやることが多すぎる。
「なんであの先生は、制作準備を日中にしているの?」 「この時間は○○の片付けをしておいてって言ったよね?」 「また残ってるの?もっと効率的にやってくれないと困るよ」
——こういった先生同士の会話、保育現場ではあるあるかもしれません。 私も、何度かドキッとしたことがあります。
でも本当は、こんな気持ちだったんです。
「やることはたくさんあるけど、子どもと向き合う時間を優先したい」
指導計画は持ち帰ってでもじっくり考えたい
私は、保育中はとにかく子ども達と向き合う時間を最優先にしていました。 一方で、指導計画のような“保育の根幹”になる書類は、しっかり時間をかけて書きたいタイプだったので、移動中にスマホのメモ機能を使って文章を練り、保育後などにパソコンで清書する、というスタイルでやっていました。
制作準備は、あえて子どもの前で
制作の準備や掲示物の準備など、子どもに見せられるものは、あえて保育中に行っていました。
「何してるの?」「それ何に使うの?」
と子ども達が興味を示してくれたり、
「こうやってみるのどう?」「わたし手伝うよ!」
とアイデアや関わりが生まれることもありました。 活動への期待も高まり、子ども達の主体性が育まれる時間にもなっていたと思います。
手間よりも“楽しさ”が大事
行事での出し物は、パネルシアターや紙芝居など園にある物を活用しつつ、もし自作する場合でも、イラスト素材は無料サイトで探して時短を心がけていました。
「大事なのは、時間をかけることよりも、子ども達が楽しめるかどうか」
この考えは、いつも忘れないようにしていました。
壁面も子ども達の作品で
クラスの壁面飾りは、保育士の手作りではなく、子ども達の作品を飾るようにしていました。
季節感を取り入れた大型制作をしたり、自由画を自由に貼れる場所を設けたり。
例えば——
- カブトムシを育てていた時期には、虫の絵でいっぱいに。
- 運動会の前には、パラバルーンやリレーの絵が並びました。
- 卒園前には「桜作りたい!」という声が上がり、クラス全員で大きな桜の木を作りました。
子ども達の「やってみたい!」を尊重しながら、保育環境を一緒に作っていく楽しさも感じていました。
第3の習慣「最優先事項を優先する」
スティーブン・R・コヴィーの『7つの習慣』では、第3の習慣をこう説明しています。
「最優先事項を優先する」
——自分の価値観に基づいた、大切なことに時間を使う
保育の仕事は本当に多忙です。
でも、「自分が一番大事にしたいことは何か?」を忘れずにいられたら、忙しさの中でも、納得感のある毎日になると思うんです。
私にとっての最優先事項は、「子どもとしっかり向き合うこと」でした。
皆さんにとっての“最優先”は、何でしょうか?
▽次の記事はこちら
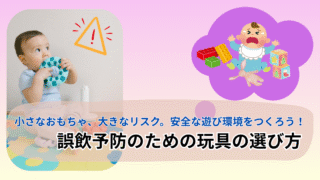

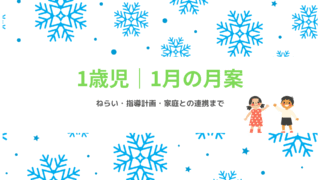
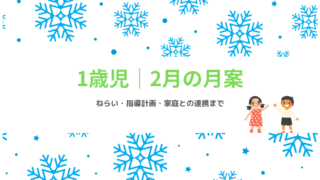

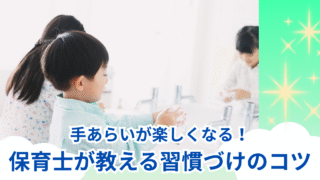

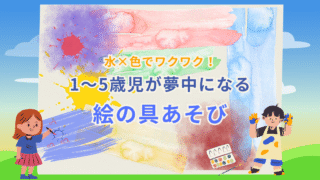
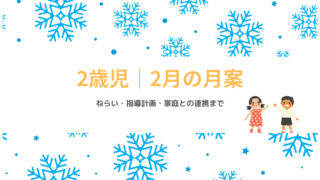

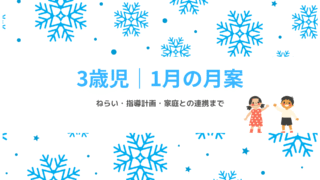
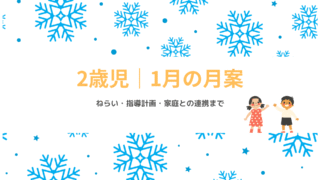
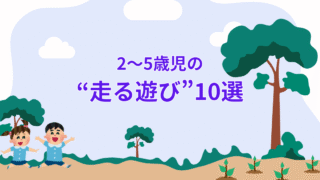
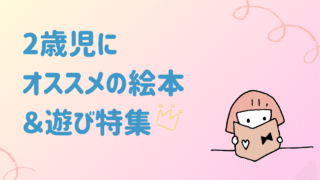

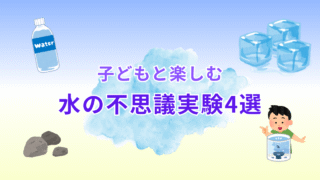
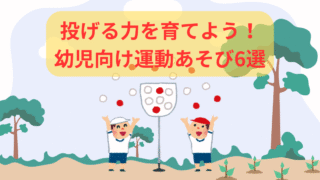
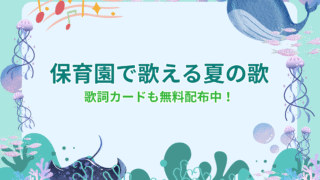




コメント