“どうにかしたい”が口ぐせだった私へ。保育士と“主体性”の話
保育現場でのモヤモヤ
「また〇〇先生、あんな決め方して…ほんと困るよね」
「子どもたちも今日は荒れてて大変だったよ…」
保育の現場って、毎日が想定外の連続。
先生同士のすれ違いや、
叩いた・泣いた・こぼしたが同時に3つくらい起こって、
思わず「もーっ!」って発狂しそうになる日もあります。
私もそうでした。
気づけば、「〇〇のせいで大変だった」「なんで私ばっかり」って、
心の中でつぶやいてばかり。
でも、ある言葉がずっと心に残っていて、少しずつ考え方が変わっていきました。
「保育士自身も、保育の大切な“環境”のひとつ」
これは、保育学校での「領域-環境-」の授業で、先生が何度も言っていた言葉です。
そのときはふんわり聞いていたけれど、現場に立つ中で、だんだんその意味が腑に落ちてきました。
「自分は、子どもの目にどんな先生として映っているだろう?」
そう考えるようになりました。
最初に意識したのは、ありきたりですが「笑顔で過ごすこと」でした。
無理して笑っていた日もありましたが、それでも続けているうちに、周りから
「しの先生って、何があっても動じないよね」
「いつも穏やかだよね」
と言われるようになりました。
自分が変わったからといって、全部がうまくいくわけではありません。
でも、「どう見られるか」ではなく「どう在りたいか」を選ぶことで、
少しずつ目の前の景色が変わっていったのを感じます。
『主体的である』という考え方
『7つの習慣』の第1の習慣、「主体的である」とは
外の出来事や他人の態度ではなく、
“自分がどう感じ、どう反応するかを自分で選ぶ”ということ。
「イライラさせられた」のではなく、「イライラしたことを選んでいる」。
そう思うとちょっと苦しくもなるけれど、同時にとても自由でもあるんですよね。
とはいえ、毎日子どもと全力で向き合って、余裕がなくなる日も当然あります。
でもそんなときほど、自分の中の“選べる自由”を思い出してみたい。
「私は今、どんな先生でいたいだろう?」
この問いを持つだけで、ほんの少しだけ、自分の立ち位置が変わっていく。
それが「主体的である」ということのはじまりなのかもしれません。
次回予告
第2の習慣:「終わりを思い描くことから始める」
― “どんな先生になりたいか”を考えるということ ―



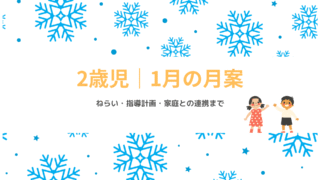
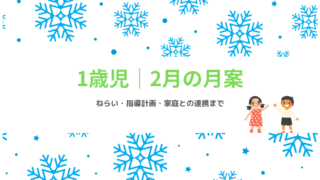
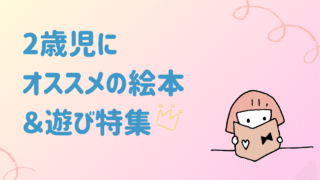
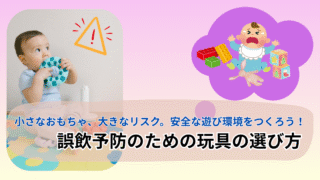
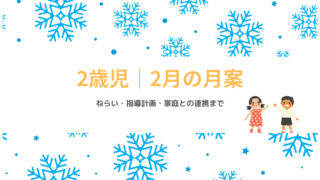

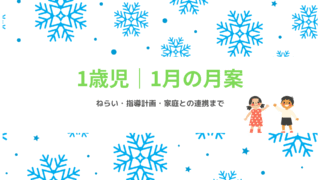

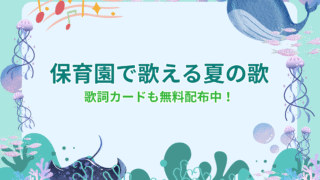
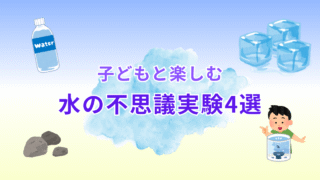
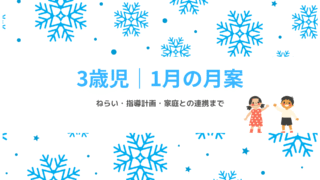
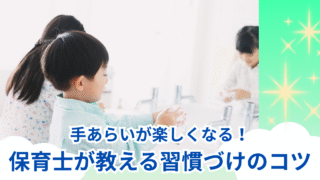


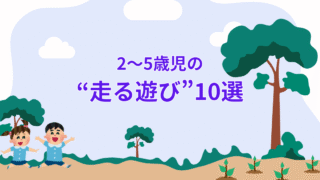
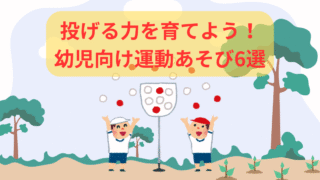
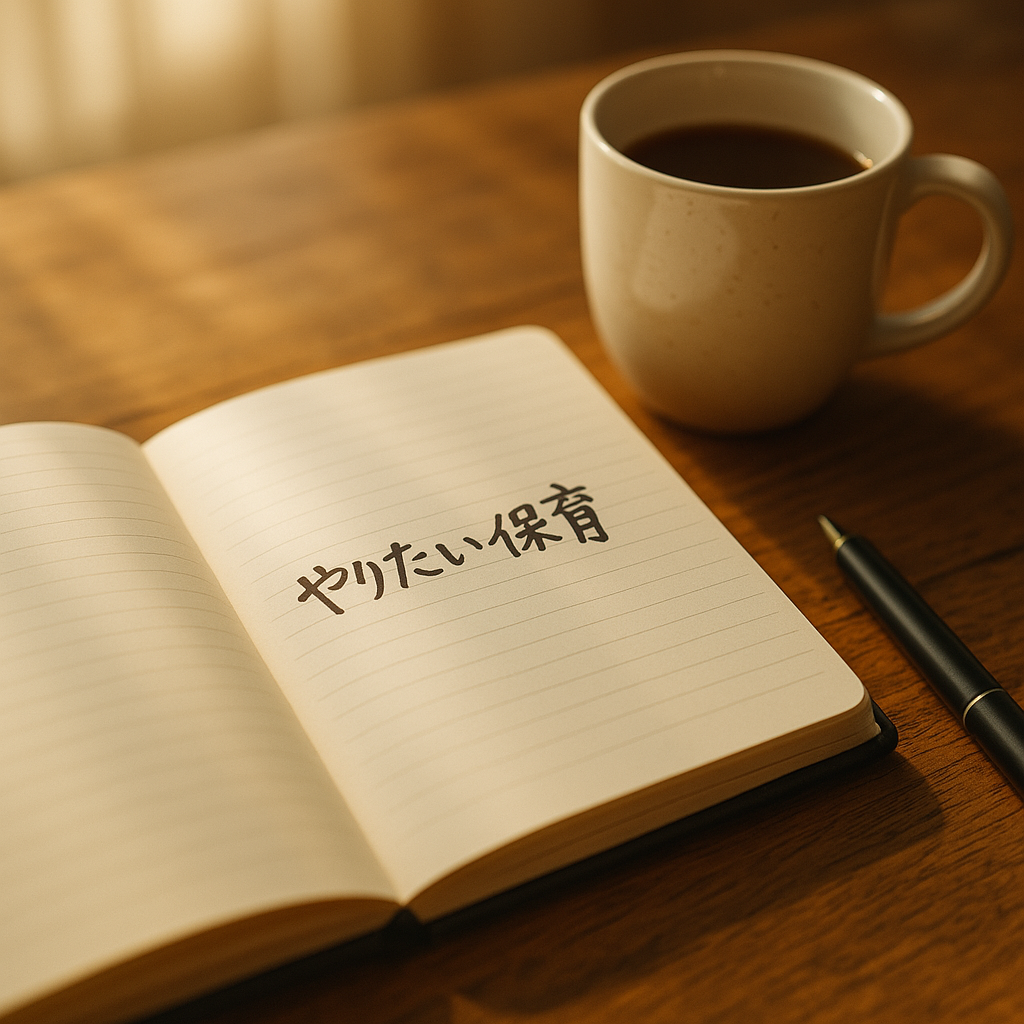
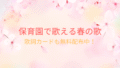

コメント