▼運動遊びのまとめ記事はこちら
幼児期に育てたい48の基本的な動き一覧とおすすめ運動遊び|遊び方・年齢別に紹介!
「投げる」力はなぜ大切?(発達の視点)
「投げる」動作は、腕の動きだけでなく、目と手の協応や体のバランス感覚、タイミングをとる力など、全身を使う運動です。運動能力の土台となるこの力は、成長とともに自然に身についていくものですが、遊びを通して繰り返し経験することで、よりしなやかに育ちます。
また「投げる」ことは、ボールあそびや的あてなど、友だちと関わる遊びの中で達成感や楽しさを感じるきっかけにもなります。
年齢別・めやすとなる投げ方の発達
子どもたちの「投げる」力は、年齢とともに少しずつ発達していきます。以下は、おおまかな発達の目安です。
- 2歳ごろ:
腕を上から下に振って投げる動きが見られます。まだ方向性や距離の調整は難しく、感覚的に投げることが多いです。 - 3歳ごろ:
前に向かって投げる動作ができるようになります。体全体の動きはまだぎこちないこともありますが、狙って投げる意識が芽生えはじめます。 - 4歳ごろ:
体重移動をしながら腕を振って投げられるようになり、距離も伸びてきます。的を狙ったり、ゲーム性のある投げ方も楽しめます。 - 5歳ごろ:
腕や体の使い方が洗練されてきて、距離や方向もコントロールしやすくなります。チームでの玉入れなど、集団でのルールあそびにも参加しやすくなります。
保育でできる「投げる」あそび5選
風船を投げてキャッチ(2~3歳向け)
軽くてゆっくり落ちる風船は、投げたりキャッチしたりする練習にぴったり。目と手の協応やタイミングを取る力が養われます。
新聞ボール投げ(2~4歳向け)
新聞紙を丸めてボールを作り、的やかごに投げ入れる遊びです。軽くて柔らかく、安全に楽しめます。
さらに、新聞を輪の形や棒状にして投げることもおすすめ。
→ フリスビーのように投げたり、やり投げ風に投げたりと、さまざまな投げ方を経験することができます。
ターゲットボードに投げる(3~5歳向け)
壁やボードに的を作り、ボールをねらって投げます。的のサイズや位置を調整することで、ねらう力や集中力を育てられます。
玉入れごっこ(3~5歳向け)
集団でかごをめがけて玉を投げ入れる伝統的な遊び。ルールがわかる年齢になったら、チーム戦や時間制限をつけるとさらに盛り上がります。
的あて遊び(3~5歳向け)
ペットボトルや空き箱を的にして、ボールを投げて倒す遊びです。倒れた時の達成感が子どもたちに人気。力加減やコントロールを意識するきっかけにもなります。
爆弾ゲーム(4~5歳向け)
2チームに分かれて、たくさんの新聞ボールを“爆弾”に見立てて投げ合います。
制限時間内に相手の陣地に多くのボールを投げ入れることが目標で、終了時に自分たちの陣地にボールが少ない方が勝ち!
→ 協力・作戦・スピード感が楽しめる遊びで、集団遊びのルール理解やチームワークも育てられます。
投げる遊びでの保育者の配慮ポイント
- 安全な距離や場所を確保する(ぶつかる危険を防ぐため)
- 遊びに夢中な子と周囲を見ていない子への声かけ
- 投げる順番やルールの確認を丁寧にすることで、トラブルの予防につながります
- 成功だけでなく「がんばってるね」「ちょっと遠くまで行ったね」と過程を肯定する声かけも大切です
おすすめ絵本や歌と合わせた遊び(PR)
遊びの導入やつながりに活用できる絵本・歌も紹介します。
「よーいどん」中川ひろたか
運動会ごっこや体を動かす遊びのきっかけにぴったり。「次は玉入れしてみようか!」と展開が広がります。
「あっ、ひっかかった」オリヴァー・ジェファーズ
投げたものが木にひっかかってしまうというユーモラスな展開。的あて遊びの前に読むと、遊びへのワクワク感が高まります。
手遊び「1と1で忍者になって」
忍者気分で手裏剣を投げるごっこ遊びに発展!空想遊びと投げる動作をつなげられます。
おわりに:日常の中で自然に「投げる」を育てるコツ
特別な道具がなくても、「新聞紙を丸めて投げる」「洗濯物カゴにボールを入れる」など、日常の中に投げる動作を取り入れることができます。「ねらってみて〜」「どっちが遠くまで投げられるかな?」と声をかけるだけで、遊びがぐっと楽しくなります。
楽しみながら、自然に育つ「投げる」力。子どもたちの発達に寄り添いながら、日々の保育に取り入れてみてくださいね。
関連記事はこちら
・幼児期に育てたい48の基本的な動き一覧とおすすめ運動遊び|遊び方・年齢別に紹介!


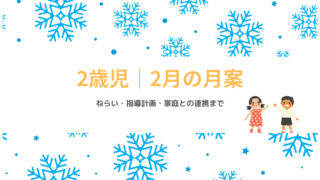

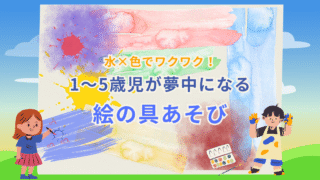
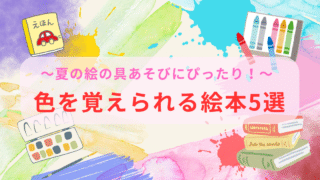
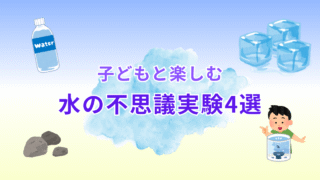

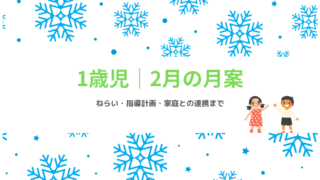
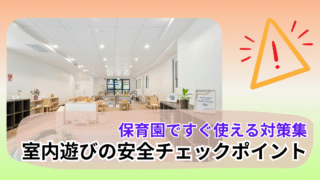

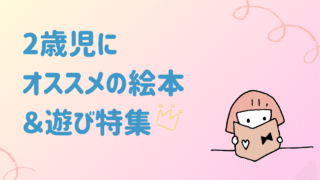

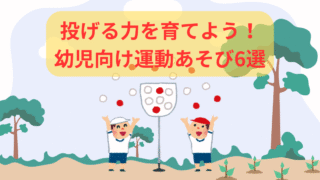
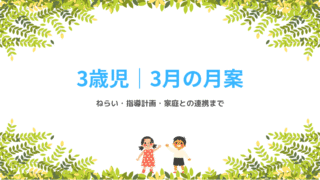
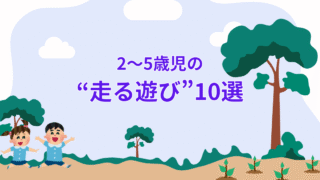

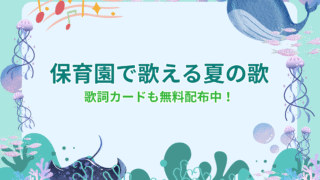
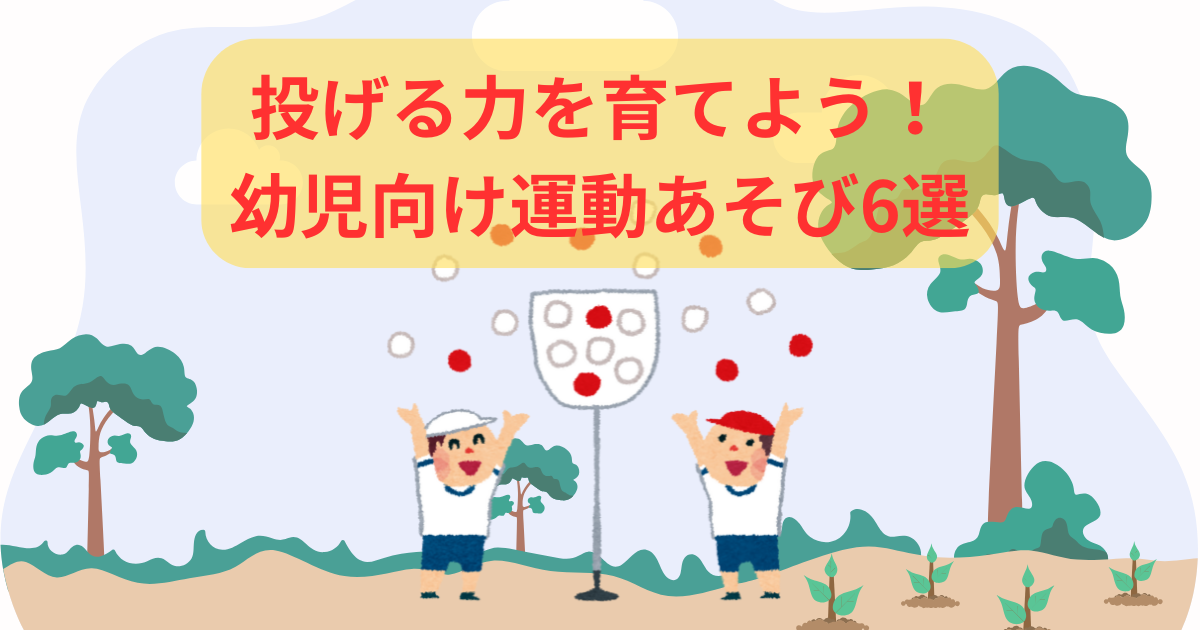


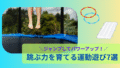
コメント