前回の記事はこちら▽
今回は第5の習慣『まず理解に徹し、そして理解される』について考えていきます。
「まず相手を理解しようとすること」
これは、スティーブン・R・コヴィーさんの『7つの習慣』の中でもとても大切にされている考え方です。
第5の習慣“まず理解に徹し、そして理解される”は、保育の現場にもぴったりだと感じています。子ども・保護者・同僚…いろんな人と関わる保育だからこそ、まずはその人の気持ちや背景に耳を傾けることが、信頼関係や安心感につながっていくと思うのです。
子ども理解が、すべての始まり
子どもが主体的に動くためには、まずはその子を理解することが出発点です。
何を感じて、何を考えて、どうしたいのか。その子の「今」に寄り添うことで、自然とやりたいことや興味関心が見えてきます。
子どもの行動には必ず理由があります。
特にトラブルの場面では、叱るよりも先に“なぜそうなったか”を丁寧に知ることが重要です。
喧嘩に「悪者」はいない
例えば、おもちゃの取り合いが起きた時。
・「壊された」「まだ遊びたかった」
・「順番なんて知らなかった」「自分も使いたかった」
どちらの子にも理由があるはずです。まずはその思いに耳を傾けることで、子どもは安心し、自分の気持ちを整理することができます。
落ち着いたタイミングで行動を振り返ることで、「叩いて痛かったかもしれない」と自分で気づく姿も見られました。
子どもの“気持ち”をキャッチするために
とはいえ、子どもはまだまだ言葉で状況を伝えるのが難しいものです。
だからこそ、保育士は普段から一人ひとりの様子を“よく観る”ことが大切だと感じます。
私がしていたのは、遊びに夢中になっている瞬間の写真を撮っておき、後からじっくり振り返ること。
「あの時こんな表情してたな」「こういう気持ちだったのかも」と想像を巡らせる時間は、子ども理解を深める助けになっていました。
保護者との関係にも“傾聴”を
子育ての悩みを相談された時、すぐにアドバイスをせず「何に一番苦しさを感じているのか」を読み取ることが大切です。
保護者の「困っている」の背景には、園では見えない家庭での姿や思いが隠れています。
「園ではこうしたらできますよ」と伝えるのは簡単ですが、それだけでは気持ちに寄り添えていない場合も。
家庭の様子や保護者の感じ方を聞き出し、共感の姿勢を持つことで、少しずつ本音を話してくれるようになります。
「話せて気が楽になった」と言っていただけた時、傾聴の力を実感しました。
保育者同士の人間関係にも
保育園という職場は、人間関係で悩むことも多いですよね。
でも、対立の根っこをたどっていくと、実はどちらも「良い保育をしたい」という気持ちから来ていることが少なくありません。
だからこそ、相手の言い分に耳を傾けてみることが大切。
十分に理解しようとする姿勢があってこそ、こちらの考えも伝わりやすくなります。
まとめ
「まず理解に徹し、そして理解される」という習慣は、保育のあらゆる場面で力を発揮します。
子ども、保護者、同僚。それぞれの“思い”を理解しようとする姿勢こそ、より良い関係づくり、そして温かい保育の第一歩です。
記事の続きはこちら▽
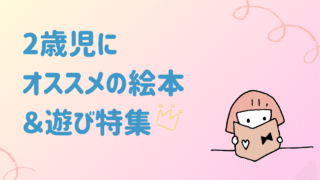
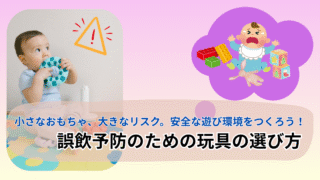


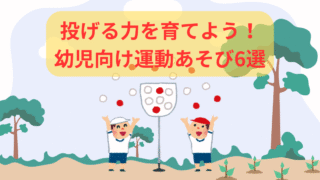
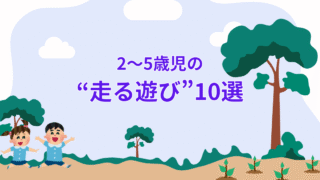
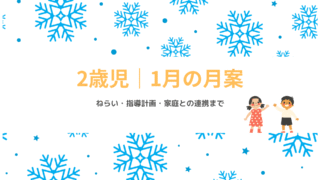


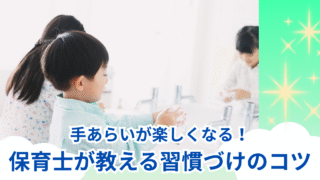
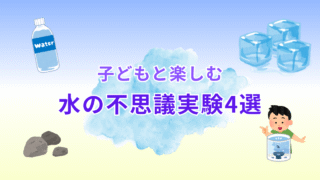
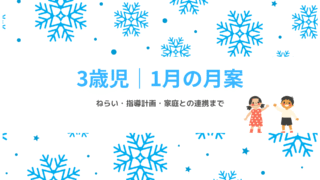
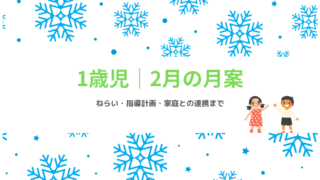
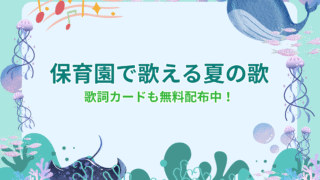


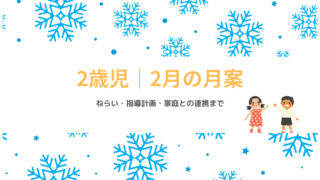
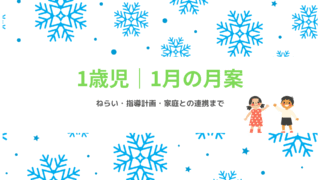
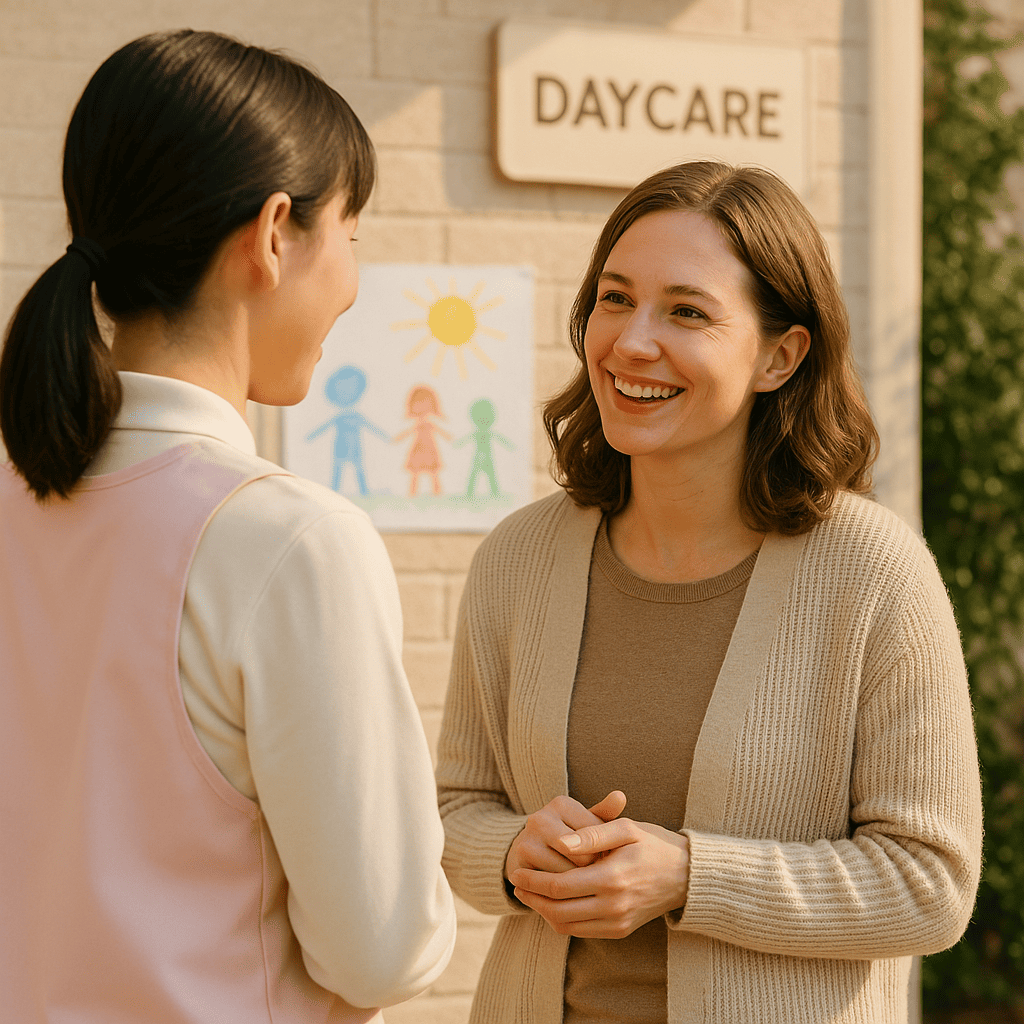



コメント