保育園・幼稚園の夏の定番「水遊び・プール遊び」。この記事では、ねらいや年齢別の遊びアイデア、安全に実施するためのポイントをわかりやすくまとめました。
計画づくりや日々の保育に役立つヒントが満載です!
水遊び・プール遊びのねらいとは?
水遊びは、子どもの五感を刺激する感覚遊びのひとつです。水の冷たさ、流れる感触、音や色の変化など、日常では味わえない経験が詰まっています。
また、バケツに水を入れる・流す・すくうなどの動作は、手先の発達や身体のバランス感覚の向上にもつながります。友だちと関わりながら遊ぶことで、思いやりや順番を待つ力など、社会性の育ちも期待できます。
さらに、暑さを心地よく乗り切るための気分転換にもなり、子どもたちの情緒が安定する効果もあります。
安全に行うために大切なポイント
実施前の準備
- 健康観察:登園時や活動前に体調をしっかり確認し、微熱や下痢、傷がある場合は参加を控えるようにします。
- 保護者からの健康情報の共有:水遊び・プール遊びの期間中は、「プールカード(健康カード)」などを活用し、保護者にも子どもの健康状態を毎日確認してもらいます。家庭と協力して、体調への意識を高めることが大切です。
- 環境整備と暑さ対策:滑りやすい場所がないかを確認し、日陰スペースやテントを設置します。また、気温だけでなく、湿度を加味した「暑さ指数(WBGT)」を参考に活動の可否を判断すると安心です。
目安としては、WBGTが28℃を超える場合は原則中止、25〜28℃は活動時間を短縮するなどの対応が推奨されます。保護者にも説明しやすく、園全体で統一した判断がしやすくなります。
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature)は、熱中症予防の指標として厚生労働省や気象庁も使用している公式な指数です。
▼厚生労働省の暑さ指数(WBGT値)に関するページhttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html
▼気象庁の熱中症アラートに関するページhttps://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/heat_alert.html
▼熱中症について詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ
保育園の熱中症対策まとめ|室内外の注意点と便利グッズ
活動中の見守り体制
- 職員配置の工夫:視界を確保できる位置で複数の保育者が見守る体制をとります。
- 目を離さない:特にプールや水をためる遊びの際は、一瞬でも目を離さないことが鉄則です。
- 声かけ:気づきやすいように、子どもとアイコンタクトをとりながら名前を呼ぶなどして関心を向け続けましょう。
【水遊び前にぜひご一読ください】
▼文部科学省の「水遊びでの事故事例と防止対策」https://www.mext.go.jp/sports/content/1397128_5-1.pdf
▼全国私立保育連盟”厚生労働省からの情報提供”より「水遊びにおける監視のポイント」https://www.zenshihoren.or.jp/uploads/topics_download/20200615120047.pdf
活動後のケア
- しっかり水分補給:脱水や熱中症予防のため、活動後は必ず水分をとらせます。
- 着替えと体温調節:濡れたままにせず、速やかに着替えを済ませて体を冷やさないようにします。
- 体調確認:遊び終わったあとの顔色や元気の様子をよく見て、少しでも違和感があれば早めの対応を。
プール使用時の留意点
- 水深は安全な範囲に(足がしっかりつく深さが基本)
- 誤飲・むせ防止の配慮:顔に水がかからない遊びを中心にするなど、怖がる子には無理をさせない
- 滑り防止マットや滑りにくいサンダルなどを使用する
年齢別のおすすめ水遊び
子どもたちの発達段階に合わせた水遊びを用意することで、より安全に、そして意欲的に楽しむことができます。年齢ごとの特徴をふまえて、遊び方や道具を工夫してみましょう。
【0〜1歳児】
この時期はまだ全身の動きが安定していないため、安心できる環境と短時間の活動が基本です。
- タライに少量の水を張って、手や足で水に触れる感触遊び
- 霧吹きやスポンジで水を感じる遊び
- 水を入れたペットボトルや透明カップでの“見て楽しむ”遊び
※慣れていない子には、無理に水に触れさせず、見ているだけでもOKです。
【2〜3歳児】
少しずつ道具を操作する力がつき、模倣遊びやごっこ遊びが盛んになる時期です。「やってみたい!」という気持ちを大切に、自由に試せる遊びを取り入れましょう。
- バケツやジョウロで水を移す・注ぐ遊び
- スポンジを使って“しぼる”感触を楽しむ
- 水風船や水車などの仕掛けおもちゃ
- 洗濯ごっこやアイス屋さんごっこなど、想像を広げるごっこ遊び
この時期は、まだ遊びがエスカレートしやすいので、保育者の声かけや場面の切り替えも大切です。
【4〜5歳児】
道具の使い方が上手になり、ルールを理解しながら友だちと関わる遊びにも発展していきます。ダイナミックな遊びも増えるため、安全管理の強化が必要です。
- 水鉄砲や的あてなどの競争・的中遊び
- 色水遊びや泡遊び(色の変化や混ざる面白さを楽しむ)
- 水流を使った実験遊び(ホースや傾斜を使って流す、運ぶ)
- チーム対抗の水運びリレーや的倒しゲームなどのルール遊び
水の感触を楽しむだけでなく、「どうしたらうまくいくか」を考える活動につなげると、思考力も育ちます。
保育の工夫と子どもとの関わり
水遊びでは、子どもが「気持ちいい」「楽しい」「面白い!」と感じる体験が何より大切です。保育士の声かけひとつで、その喜びをさらに広げたり、安心感を持たせたりすることができます。
声かけの工夫
- 「つめた〜い!気持ちいいね!」
- 「バシャバシャって音、カエルさんみたいだね」
- 「どうやったらもっと遠くまで飛ぶかな?」
子どもが発見したことに共感したり、ちょっとした疑問を投げかけたりすることで、遊びがより深くなっていきます。
発達に合わせた援助
- 初めての水遊びには“安心できる先生のそば”を用意する
- 嫌がる子に無理はさせず、少しずつ慣れるよう工夫する
- 活動時間を調整して、疲れすぎないように配慮する
活動のしめくくりも大切に
- 片付けも遊びにして一緒に楽しむ
- 着替えながら「どんな遊びが楽しかった?」と振り返る
- クラスでのふり返りや絵日記などに発展させるのもおすすめです
おわりに
水遊びやプール遊びは、ただ「楽しむ」だけでなく、子どもの育ちを豊かにする大切な活動です。安全を第一に、年齢や発達に応じた関わりを通して、夏ならではの体験を思いきり楽しめるようにしたいですね。
日々の実践の中で「こうするとスムーズだった」「こんな反応があった」などの気づきも、ぜひ周囲と共有しながら保育に活かしていきましょう。
関連記事はこちら
【水遊び・プール遊び関連】
・【年齢別】家庭で楽しむ水遊び・プール遊び|0〜5歳におすすめの遊び&安全対策
【暑い時の安全対策】
・「子どもが水分を取らない…」保育現場でできる水分補給の工夫と共有のコツ
【暑い日におすすめな「涼」を感じる室内遊び】
・【0・1歳児向け】暑い日の室内あそび10選|家庭でも保育園でもできる涼しい遊び【前編】
・【2・3歳児向け】暑い日の室内あそび10選(前編)|感触・色・風で楽しむ涼しいあそび
・【4・5歳児向け】暑い日の室内あそび10選(前編)|保育園や家庭でできる“涼しさ”体験
【水遊びアイデア&絵本】


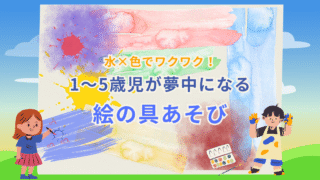

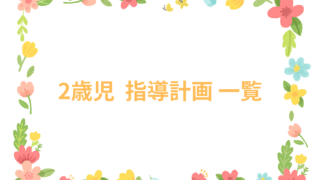
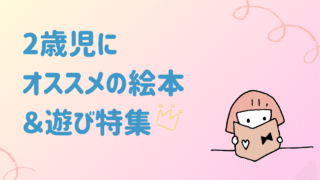
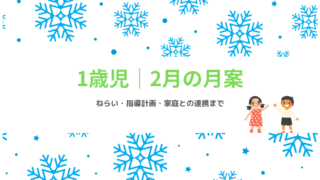
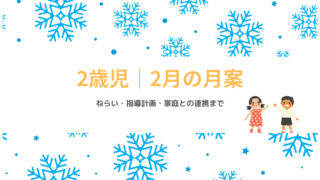
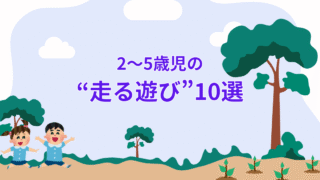

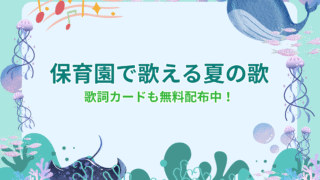
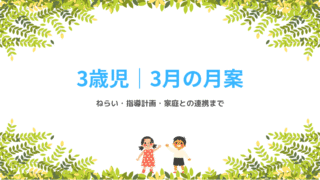
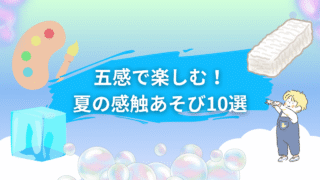
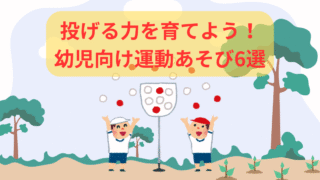

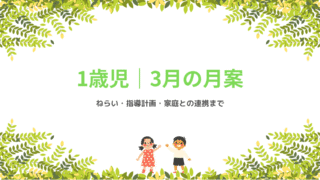

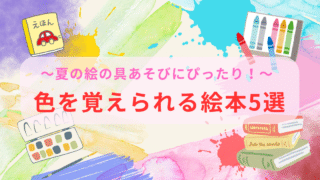

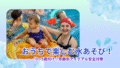
コメント