「保育って本当に人と人との関わりの連続。」
子どもたちとの関係、保護者との関係、同僚との関係……そして、自分自身との向き合い。
このシリーズでは、スティーブン・R・コヴィーの名著『7つの習慣』を保育の現場にあてはめながら、よりよい関わり方や心の持ちようを考えてきました。
もし今、少し疲れていたり、モヤモヤしていたりしたら──
どれかひとつの習慣が、そっと背中を押してくれるかもしれません。
【第1の習慣】主体的である
“まず自分のあり方を見つめることから”
「私ばっかりやってる気がする…」と感じたとき、まずできることは“自分の選び方”を見つめ直すこと。
小さな“選び”の積み重ねが、心の余裕を生んでくれます。
→ 記事を読む
【第2の習慣】終わりを思い描くことから始める
“子どもの育ちから逆算する”
「どんな保育士でいたい?」と聞かれると難しくても、
「子どもたちに、どう育ってほしい?」なら、答えが見えてくるかもしれません。
→ 記事を読む
【第3の習慣】最優先事項を優先する
“今、本当に大切なことに目を向ける”
日々のバタバタに追われていると、大切なことほど後回しに…。
限られた時間の中で“優先すべきこと”を選ぶ力が、明日の保育を変えてくれます。
→ 記事を読む
【第4の習慣】Win-Winを考える
“子ども・保護者・保育者、みんなが心地よく”
「どちらかが我慢」ではなく、「みんなが納得できる」関係ってどんなもの?
子どもとのやりとり、保護者対応、職員間の連携など、日々の中にヒントが散りばめられています。
→ 記事を読む
【第5の習慣】まず理解に徹し、そして理解される
“聴くことは、保育の最強スキル”
子どもの言葉、保護者の声、職場の仲間の思い──
まず“理解しよう”とする姿勢が、安心と信頼につながっていきます。
→ 記事を読む
【第6の習慣】シナジーを創り出す
“違いを活かすと、もっといいチームになる”
得意なこと、苦手なことはみんな違う。
「一人じゃできなかった!」が、「一緒だからできた!」に変わる瞬間を大切に。
→ 記事を読む
【第7の習慣】刃を研ぐ
“自分を整えることは、子どもたちにも伝わる”
感情が揺れる瞬間、疲れを感じる日々。
そんな時こそ、自分の心と体を整えることが、保育の質につながります。
→ 記事を読む
おわりに
「なんだか最近、うまくいかないな…」
そんな時に、思い出してもらえるシリーズであったら嬉しいです。
日々の保育の中で、小さな気づきや心のゆとりを持てますように。
気になった習慣から、ぜひ読んでみてくださいね。
📚もっと深く知りたい方へ【PR】
子どもとの関わりや、保育の仕事にも役立つヒントが詰まった一冊です。
▽漫画版も分かりやすくおすすめです。
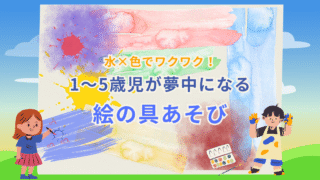
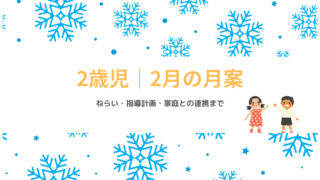

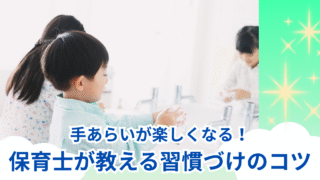
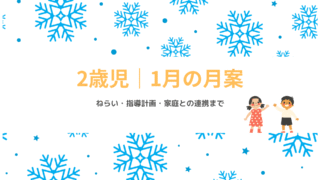
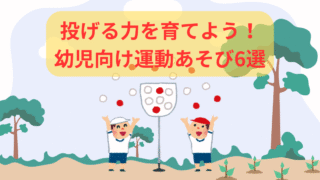

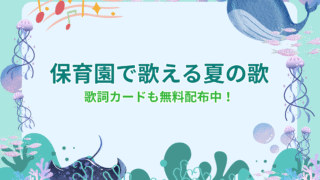
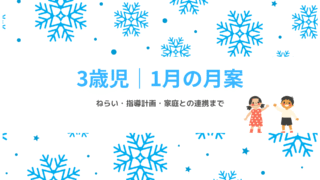
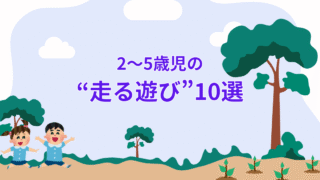
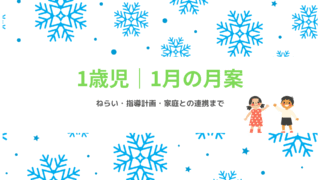
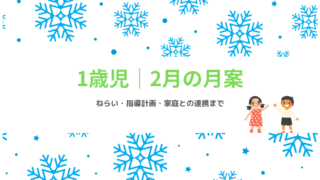

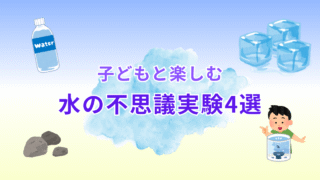


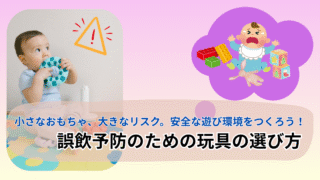
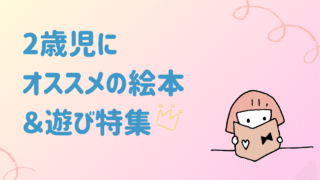




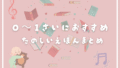
コメント