▽前回の記事はこちらです。
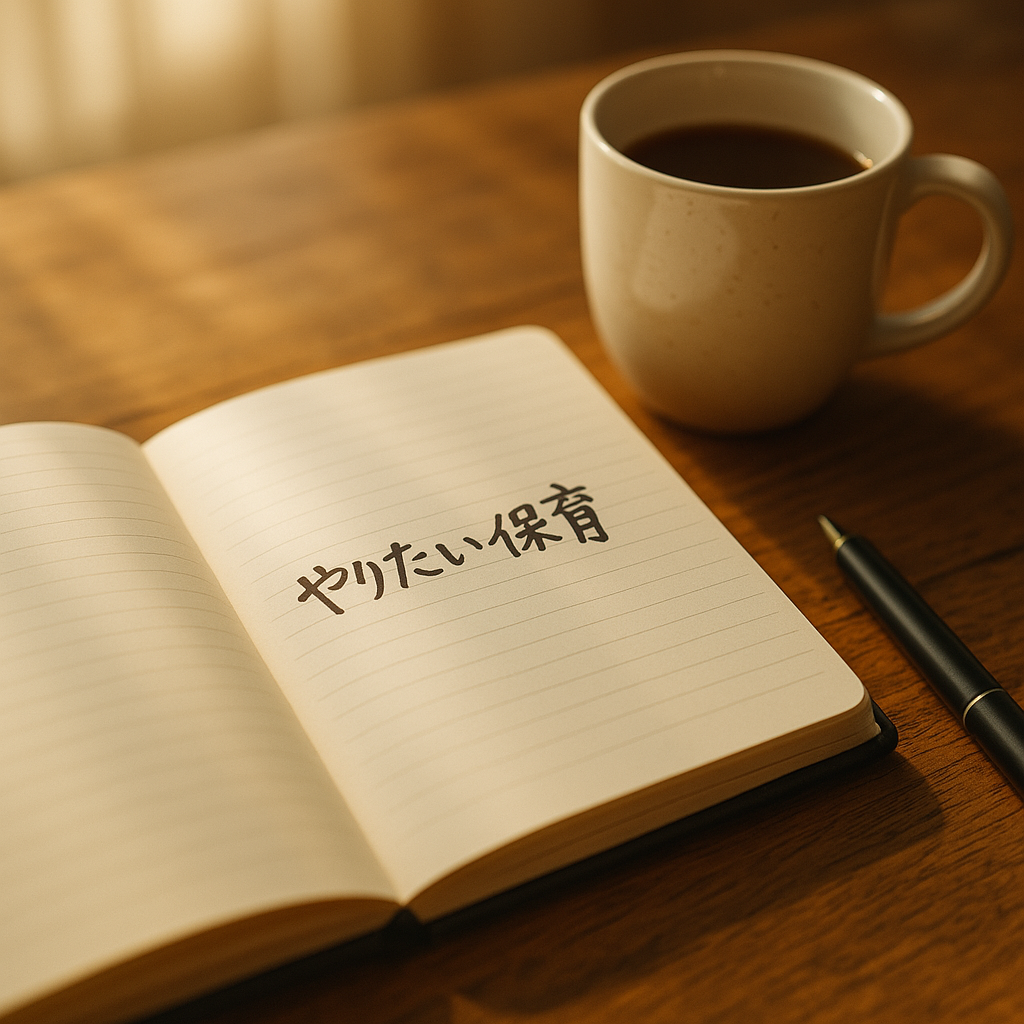
「なりたい自分」って、難しくないですか?
「どんな自分になりたい?」って、時々聞かれることがあります。
でも、意外とすぐに答えられなかったりしませんか?
自分のことになると、客観的に考えるのが難しい。
でも、不思議と子どものことだと、すっと言葉が出てくるんです。
「友達の気持ちをわかってあげられる子になってほしい」
「自分のアイデアを大事にできる子になってほしい」
「素直で明るく、挑戦を楽しめる子になってほしい」
——実はそれ、あなた自身が“なりたい姿”なのかもしれません。
【第2の習慣】「終わりを思い描くことから始める」って?
『7つの習慣』で語られる第2の習慣は、
「終わりを思い描くことから始める」という言葉です。
これは、人生や仕事を進めるときに、
まず“最終的にどうなりたいか”を思い描こう、という考え方。
保育に置き換えると、
「どんな保育士でありたいか」
「子どもにどう育ってほしいか」
——その“ゴール”を思い描いておくことで、
毎日の保育の中で選ぶ言葉や関わり方がブレにくくなります。
「育ってほしい姿」を書き出して気づいたこと
私が5歳児クラスを担任していた年。
新年度に入ってすぐ、「今年、どんなクラスにしたいか?」を考える時間がありました。
子どもたちの姿を思い描きながら、私はこんなふうに書きだしました:
- 優しい子:友達の思いに共感できる子。お互いを認め合えるから、仲が深まり、毎日が楽しくなる。
- 考えやアイデアを言える子:自分の思いを安心して伝えられることで、活動がより楽しく、学びが深くなる。
- 挑戦できる子:難しいことにも諦めずに取り組める子。できた時の感動を知ってほしい。
- 素直で明るい子:気持ちのいい挨拶ができて、友達の良さを素直に「すごいね」って言える子。自分の強みも受け入れられる子。
書き出していて、ふと気づいたんです。
「これ…私がなりたい姿だな」って。
子どもへの願いは、自分の理想かもしれない
「自分はどうありたいか」って、考えるのは難しい。
でも「子どもにどう育ってほしいか」なら、自然に言葉が出てくる。
もしかしたらその中に、
「こういう先生でいたい」
「こんな人でありたい」
——そんな自分の理想が映っているのかもしれません。
終わりを思い描くことで、選択に迷わなくなる
理想の自分、なりたい保育士像を思い描いておくと、
迷ったときに立ち返る“軸”ができます。
たとえば、「今日はちょっと機嫌が悪いな…」って日でも、
「私は“どんなときも穏やかな先生”でいたい」と決めていれば、
感情の波に流されすぎずにすみます。
それは、子どもにも安心を与える環境にも繋がっていきます。
今日のヒント
「こんな子に育ってほしい」は、あなた自身の“なりたい姿”かもしれない。
自分の理想の姿を、まず言葉にしてみよう。
それは、毎日の保育に“芯”をくれる習慣になる。
次回は第3の習慣「最優先事項を優先する」
多忙な毎日の中、一番大切にしたいことは?
“やること”に追われる日々から抜け出すには?
次の記事で解説します。

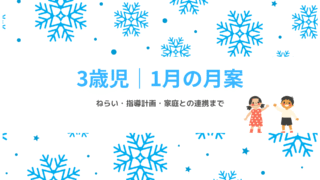

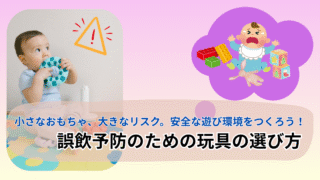
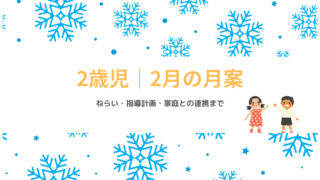
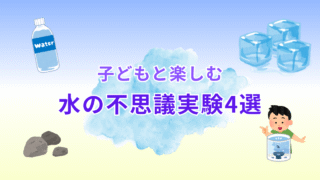


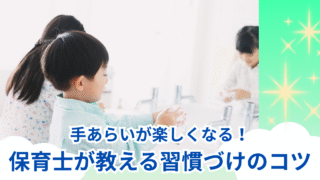

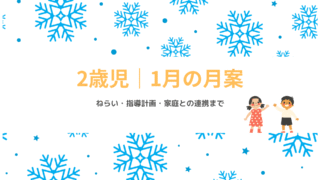
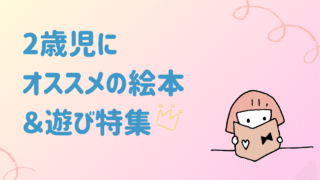
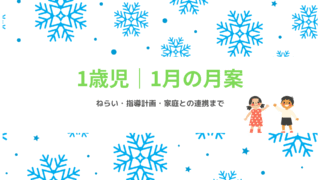
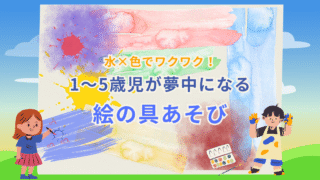
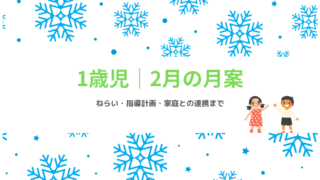
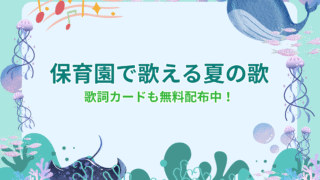

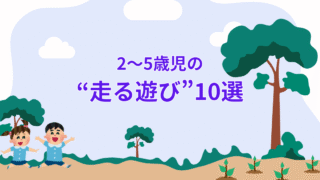
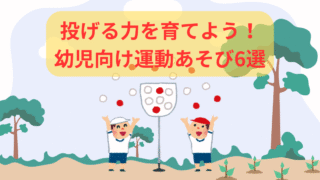

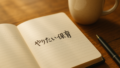

コメント