乳幼児期は、何でも口に入れて確かめる時期。特に0~3歳頃の子どもたちは、思わぬものを飲み込んでしまう「誤飲」のリスクが高く、日々の保育や家庭生活の中で細心の注意が必要です。
本記事では、誤飲を防ぐために重要な「玩具選び」のポイントを、保育者や保護者の立場からわかりやすく解説します。事故を未然に防ぎ、安心して遊べる環境づくりに役立ててください。
なぜ誤飲事故が起きるのか?
乳幼児は「口に入れる」ことで物を確かめようとします。そのため、小さなものが手に届く場所にあると、すぐに口に入れてしまうのです。
また、乳児は嚥下(飲み込む動き)が未熟なため、わずかな大きさのものでも窒息につながる危険性があります。誤飲事故は、ほんの一瞬の油断から起こるもの。だからこそ、「そもそも口に入らないようにする」ことが、最も効果的な予防策なのです。
誤飲予防に役立つ「玩具の選び方」5つのポイント
① 誤飲チェッカーでサイズ確認を
最も基本的な対策は、誤飲チェッカー(誤飲スケール)を使ってサイズを確認すること。これは、直径約3.9cm×長さ約5.1cmの円筒状の道具で、これにすっぽり入るサイズのおもちゃは、誤飲の危険性があるとされています。
市販品のほか、トイレットペーパーの芯やフィルムケースを代用品として使用する保育現場もあります。
3歳未満の子どもには、「誤飲チェッカーに入るサイズのおもちゃ」はNG!
詳しくはこちらを参照にしてみてください。(外部リンクに飛びます)
子どもの事故防止教材 「誤飲チェッカー」「誤飲防止ルーラー」 | 一般社団法人 日本家族計画協会
② 対象年齢を確認する
市販の玩具には、必ず対象年齢が記載されています。これは発達段階に合わせた遊び方だけでなく、安全性の観点からも定められているもの。
特に「3歳以上対象」と明記されたおもちゃは、3歳未満の子どもが使用すると誤飲事故につながる可能性があるため、年齢の目安を守ることが大切です。
クラスで使用するおもちゃは、対象年齢別に整理・保管すると◎
③ 壊れにくく、安全な素材を選ぶ
玩具の素材にも注意が必要です。特に以下のような点をチェックしましょう。
- 小さな部品が接着されているおもちゃ(タイヤ・目玉など)が簡単に外れないか
- 木製のおもちゃでささくれや欠けがないか
- 縫製された布製品で糸のほつれや綿の露出がないか
また、使用頻度が高いおもちゃほど劣化が早いため、定期的な点検や清掃を行うことも重要です。
④ 食べ物に見えるおもちゃは避ける
本物そっくりの食品サンプルや、ビーズ・スライムのような感触玩具は、子どもが「食べ物だ」と思い込んで口にしてしまうこともあります。
- 「お寿司のおもちゃ」「おままごとの小さなパーツ」「ゼリー風のおもちゃ」などは特に注意が必要です。
- 見た目がリアルであればあるほど誤飲リスクが高まると考えておきましょう。
⑤ 誤飲事故の事例を知っておく
具体的な事故事例を知ることは、リスクへの感度を高めるために非常に有効です。
実際にあった誤飲事故の例
- ボタン電池を飲み込み、食道に穴があいて緊急手術
- 磁石入りブロックを複数飲み込み、腸に挟まり腸閉塞に
- ビーズやペットボトルキャップを喉に詰まらせて呼吸困難に
保育の現場でも「これは大丈夫」と思っていたおもちゃが、子どもの成長や遊び方の変化によって危険になることもあるため、注意深く見守ることが必要です。
保育現場でできる工夫と管理体制
年齢別におもちゃを仕分け・管理する
- 色別のカゴや棚を使って「0〜2歳用」「3歳以上用」と見た目で分かるように整理
- 「異年齢保育」や「兄弟児の持ち込みおもちゃ」には特に注意が必要
床に落ちた部品はすぐに拾う習慣を
- 活動後には必ず落下物・破損チェックの時間を設けると安心
- 「お口に入れたおもちゃは消毒後に回収」など、ルールを明確に
保護者との連携も大切に
保育園・幼稚園では、安全な遊び環境を整えることに注力していますが、家庭でも同じ基準を共有できると誤飲リスクはさらに下がります。
- 保護者向けおたよりや掲示板で、「誤飲しやすいおもちゃ」「おうちでも気をつけたいこと」を共有
- 誕生日プレゼントや持ち込み玩具の相談があった際には、対象年齢やサイズに注意するようお伝えする
まとめ:誤飲を防ぐために、今日からできること
| チェックポイント | 実践例 |
|---|---|
| おもちゃのサイズ | 誤飲チェッカーで確認/トイレットペーパーの芯で代用 |
| 対象年齢の確認 | 3歳以上対象の玩具は未満児に使用しない |
| 壊れにくさ | 部品が取れないか/木製・布製の劣化確認 |
| 見た目 | 食品サンプル風、リアルすぎる形状は避ける |
| 点検・保管 | 年齢別に分類・破損品は即回収/定期清掃 |
| 保護者への周知 | おたよりで情報共有/安全な持ち込みのお願い |
おわりに
誤飲事故は、ほんの一瞬の隙を突いて起こります。ですが、正しい知識と日常の工夫で予防することは十分に可能です。
「このおもちゃ、本当に安全かな?」
そう思ったときこそ、見直しのタイミング。子どもたちの「遊びたい!」という気持ちを大切にしながら、安心して楽しめる環境づくりを一緒に続けていきましょう。
関連記事はこちら
・保育園での室内遊びの安全チェックポイント|事故防止実践ガイド
・誤飲予防に役立つチェックリスト(PDFダウンロード可)▶準備中

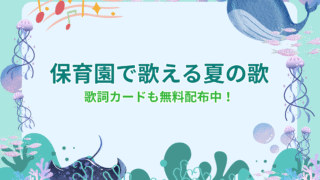

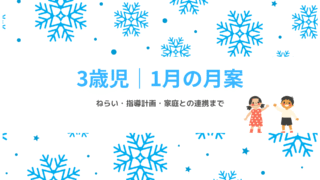
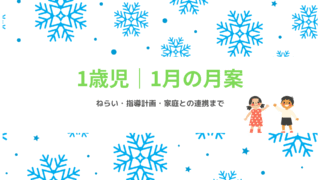
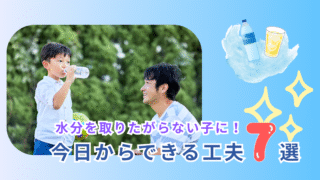
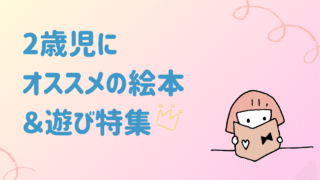
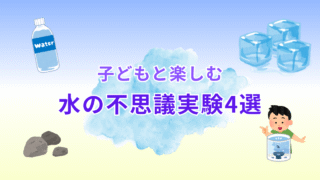
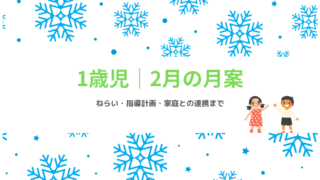
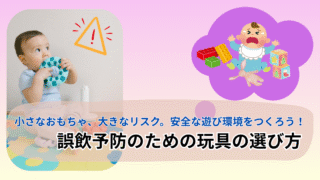
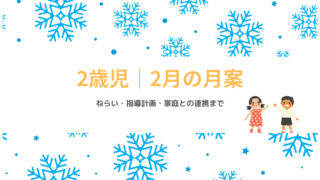
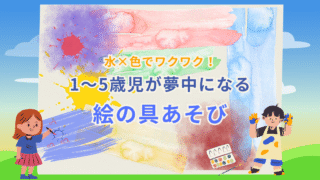
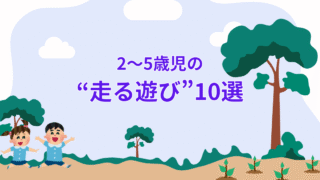
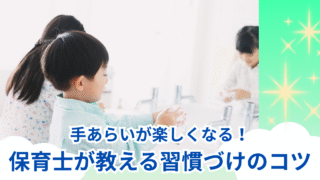

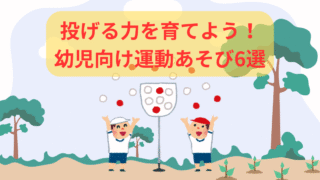
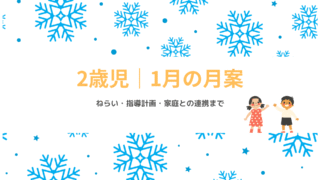

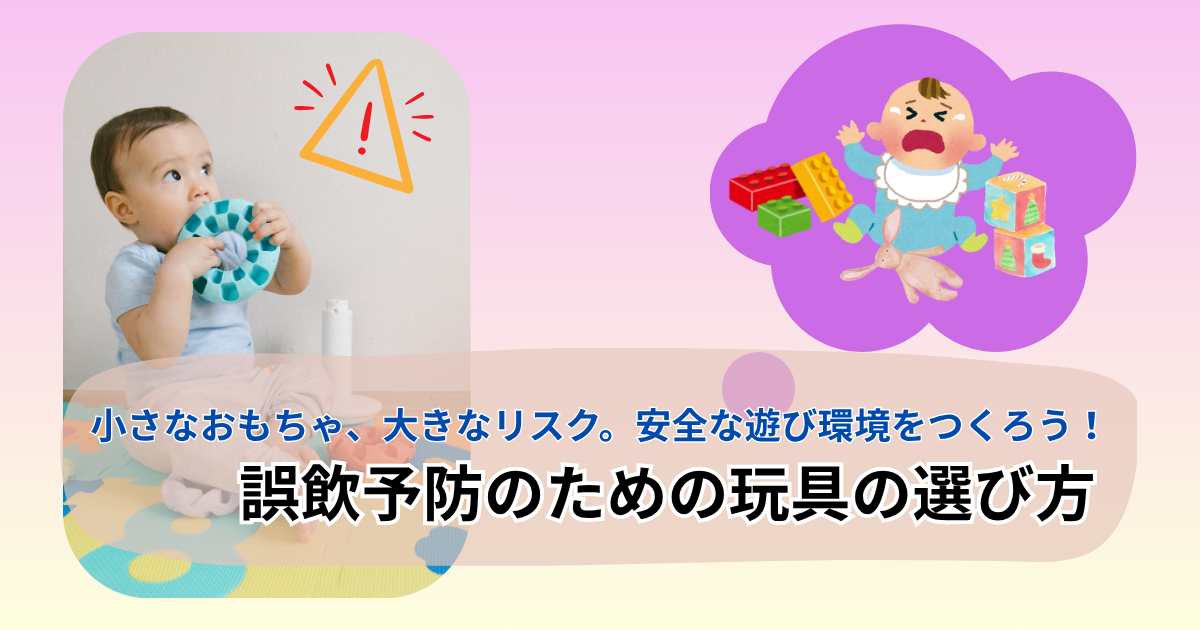
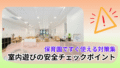
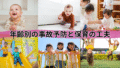
コメント