前回の記事はこちら▽
〜保育者自身が整うことで、良い保育が生まれる〜
「刃を研ぐとは、自己の持つ最大の資源である“自分自身”を磨き続けること。」
――『7つの習慣』スティーブン・R・コヴィー
保育の現場は、毎日が忙しくてあっという間。
子どもたちのために動き続けるなかで、自分自身のことはつい後回しになりがちですよね。
でも、保育者が心と体を整えていると、子どもたちへの関わりにも自然と余裕が生まれていきます。
今回は、そんな“自分を整える時間=刃を研ぐ”ことについて、私自身の体験をもとに綴ってみたいと思います。
小さな深呼吸がくれる冷静さ
トラブルが起きてバタバタしているとき、つい感情的になりそうになることもありますよね。
そんな時、私は「深呼吸をひとつ」して、「多少遅れても大丈夫」「何とかなる」と心の中でつぶやくようにしています。
それだけで、不思議と気持ちが落ち着いて、子どもにも優しく関われることが多いんです。
また、保育中に「がんばるぞー!」と一声出してみると、子どもたちも「おー!!」と返してくれて。その素直な反応に、こちらまで元気をもらえたりします。
ほんの10分でも、ぐっとラクに
休憩の合間に、10分だけ目を閉じてみる。
たとえ眠れなくても、午後の保育に向けて気持ちがスッと整う感覚があります。
また、書類が多くなる月末などは、他クラスと連携して合同保育を行い、交代で「抜け時間」を作ってもらっていました。
その間に集中して作業を進められると、残業も減らせて気持ちにも余裕が持てるように。
子どもたちも、いつもと違う友だちとの遊びを楽しんでいました。
「ありがとう」が巡ると、職場が温かくなる
忙しい日常のなかでも、職員同士で「ありがとう」を伝え合うように意識しています。
たった一言でも「気づいてくれてるんだ」と、心がふっと軽くなる感じがします。
お互いが気持ちよく働けるようになる、ちいさくて大きな習慣です。
子どもにも「ほっとできる場所」を
子どもたちにも、気持ちを落ち着けられる場所があるといいなと思い、
保育室の一角に、段ボールハウスやパーテーションで囲った“ひとりになれるスペース”を用意していました。
その中で本を読んだり、静かに過ごしたり。
気づけば自然と、気持ちを整えたいときに子どもたちがその場所を選ぶようになっていました。
学ぶことが、前向きな力になる
休日に時間があるときは、外部研修に参加したり、本を読んだりすることもあります。
新しいことを知ると、「明日やってみようかな」と気持ちが前向きになりますし、
実践の引き出しが増えることで、保育への自信にもつながっていきます。
おわりに
「刃を研ぐ」ことは、見た目には分かりにくいけれど、
保育を続けていくうえでとても大切なことだと感じています。
まずは、自分自身が満たされること。
そうすることで、子どもたちにも穏やかなエネルギーを届けることができるはずです。
どうか、自分の心と体にもやさしくできる時間を、大切にしてくださいね。
【保育士×7つの習慣】全7回の記事のまとめはこちら

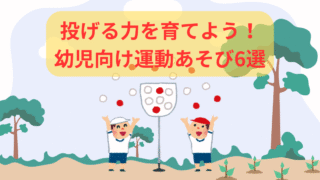
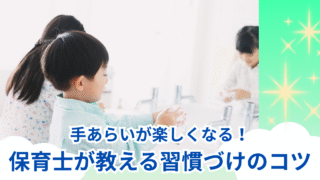

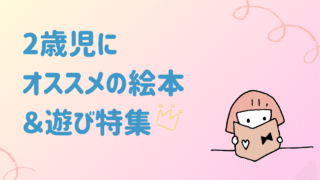
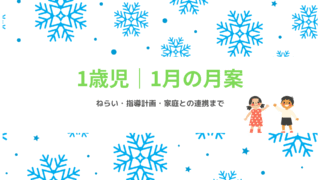

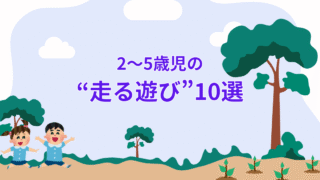
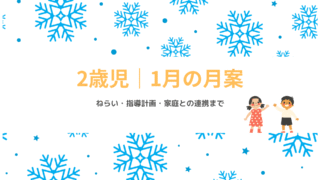
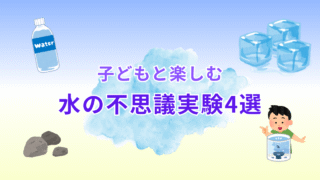
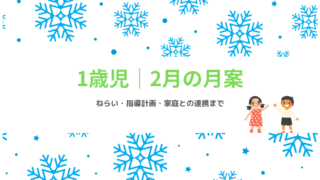
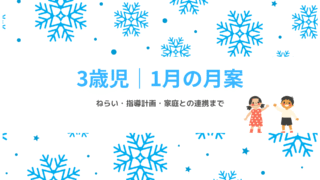
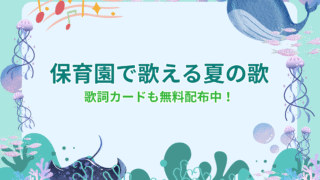
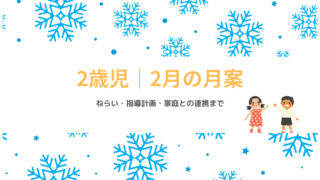
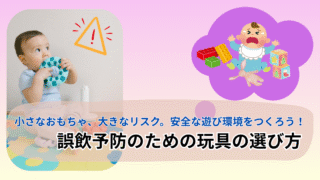








コメント